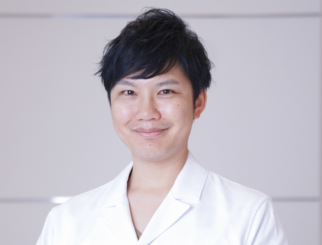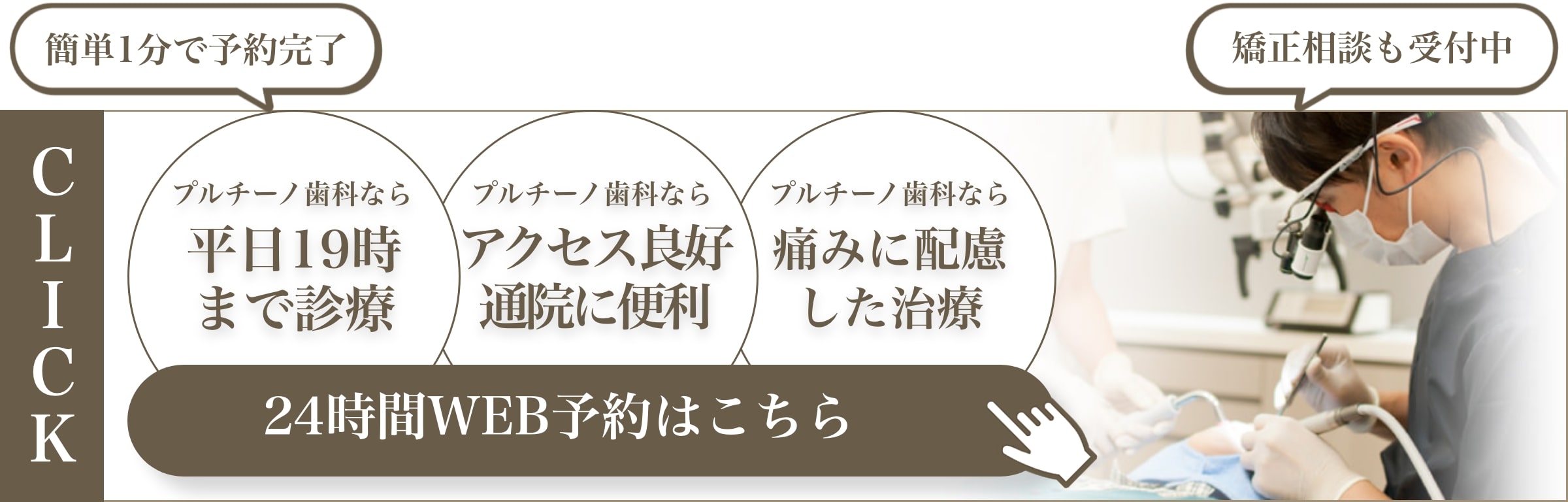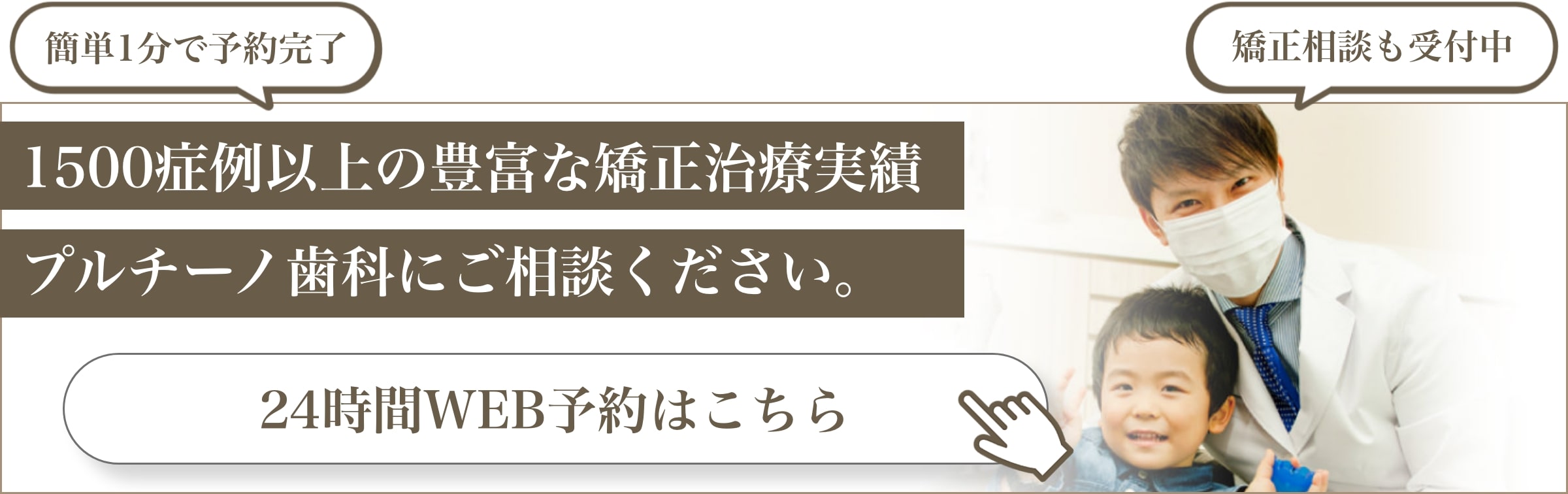医院からのお知らせ
抜歯にかかる費用は?親知らずの抜歯前に知っておきたいポイントを解説!
25.03.20
カテゴリ:医院からのお知らせ
親知らずを抜歯したい方や、虫歯や歯周病などで抜歯をしなくてはならない方は、抜歯の料金が気になる方もいるでしょう。
今回は、抜歯にかかる費用について解説した後、親知らずの抜歯をする方が、事前に知っておきたいポイントについて解説していきます。
抜歯は保険治療でできるの?
虫歯や歯周病が原因で抜歯をする場合、また乳歯が遅くまで残っている状態の場合など、ほとんどのケースで保険が適用になります。
ただし、矯正治療のために抜歯をする場合は、病気の治療ではないので、自費治療になります。
抜歯にかかる費用

抜歯にかかる費用は、抜く歯と目的によって異なります。抜く歯・目的に分けて費用を解説します。
乳歯の抜歯
乳歯は従来、自然に抜けて永久歯に生え変わりますが、稀に永久歯への交換がスムーズにいかずに、なかなか乳歯が抜けないことがあります。
そのような乳歯を抜歯するのにかかる費用は保険適用の3割負担で1,000円〜1,500円程度です。子供の場合は、自治体によって異なりますが、医療費が助成される場合が多いです。医療費の窓口負担額が決められていますので、無料〜500円程度の決められた支払いになります。
前歯・小臼歯
前歯や小臼歯(前から数えて5番目までの歯)を抜歯する場合の費用は、保険適用の3割負担で1,500円〜3,000円程度です。
前歯の場合は、抜歯後に歯が無い状態になると見た目が悪くなってしまうことがあるので、抜歯と同時に仮歯を装着したり、義歯を装着することがあります。
その場合は別途、仮歯や義歯の費用がかかります。
大臼歯の場合
大臼歯(前から数えて6番目以降の歯)を抜歯する場合の費用は、保険適用の3割負担で3,000円〜5,000円程度です。
通常の大臼歯は3,000円程度になりますが、大臼歯の中でも親知らず場合は、生え方によって費用が異なります。他の大臼歯と同様に真っ直ぐに生えている場合は3,000円程度ですが、横向きに埋まっている場合、全部または一部分が埋まっている場合には、難抜歯となり5,000円程度です。
複雑な抜歯になる症例では、CT撮影をする場合があり、CT撮影をする際には別途3,500円程度がかかります。
矯正治療に関わる抜歯
矯正治療では、歯を並べるスペースが足りない場合に抜歯をすることがあります。矯正治療のための抜歯は自費治療になり、1本あたり5,000円〜1万5,000円程度です。
親知らずは必ず抜いた方が良いの?

親知らずがある方は「抜歯した方がいいの?」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。実は親知らずは、必ずしも抜かなければいけないわけではありません。
真っ直ぐ生えており、トラブルを起こしていない、また起こす可能性の低い歯は抜く必要はありません。
親知らずを抜いた方が良いケース、抜かなくても良いケースについて紹介します。
親知らずを抜いた方が良いケース
次のようなケースは、抜いた方が良いと言えるでしょう。今現在、痛みなどがなければ緊急性はありませんが、都合の良いタイミングで抜歯できるように計画を立てるのが良いです。
智歯周囲炎を繰り返している
智歯周囲炎は、親知らず(智歯)の周囲で起こる歯茎の炎症のことを指します。
親知らずが半分埋まっている場合などに起こりやすくなります。一度、智歯周囲炎になると、症状が治まっても再び腫れや痛みを繰り返すことが多いです。
智歯周囲炎を放置すると、隣の歯を支えている骨が溶けてしまうリスクもあります。抜歯した方が良いでしょう。
虫歯や歯周病になっている
虫歯や歯周病になっている場合は、抜歯した方が良い場合が多いです。
親知らずは、お口の中の一番奥に位置しており、十分に歯ブラシが届かないことがあります。このようなケースでは、治療をしても虫歯や歯周病を繰り返すことが多く、治療器具も届きづらく十分に治療ができないことがあります。また、治療をしても虫歯や歯周病を繰り返すことが多いので、抜歯を勧めることが多いです。
親知らずが原因で手前の歯が虫歯になっている
親知らず周囲に汚れが溜まりやすいことが原因で手前の歯が虫歯になっている場合は、虫歯の治療をするのと同時に、虫歯の原因となっている親知らずは抜歯する方が良いでしょう。
噛んだ時に親知らずが周囲の粘膜や歯茎を傷つけている
噛み合う歯がない歯は、どんどん伸びてきてしまいます。親知らずが伸びてしまうと、歯茎や粘膜に触れて傷つけてしまうことがあります。そのような場合には、抜歯する方が良いでしょう。
歯並びに悪影響を与えている
親知らずが横向きになっている場合など、手前の歯を押しているようなケースでは、歯並びが徐々に悪くなってしまうことがあります。
歯並びに悪影響を与えている場合には、良い歯並びを保つために抜歯を検討した方が良い場合があります。
親知らずを抜かなくても良いケース
次のようなケースでは、親知らずを抜かなくて良いです。ただし状態が変化することもありますので、定期検診をしながら経過をみていくのが良いでしょう。
正常に真っ直ぐ生えている
親知らずが正常に真っ直ぐ生えていて、トラブルの無い場合は、必ずしも抜歯する必要はありません。特に噛み合う反対側の歯も生えていて、しっかり噛み合っている場合には、機能しているので、抜く必要は無いでしょう。
完全に埋まっている
親知らずが完全に顎の骨の中に埋まっている場合は、必ずしも抜歯する必要はありません。
痛みを感じず、他の歯に悪影響を与えていないようであれば、放置しておいて問題ないでしょう。
抜歯は痛みがあるの?
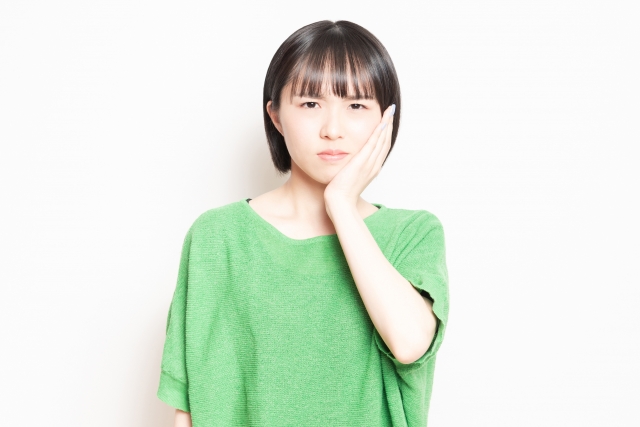
抜歯をする場合の心配事の一つに「痛み」があげられるのではないでしょうか。
抜歯の痛みについても解説していきます。
抜歯をする時に痛みはあるの?
歯を抜く時は、局所麻酔をするので、痛みを感じることはありません。
ただし顎の骨を押すような感じや、触れられている感じはあります。
局所麻酔の効き方には個人差があるので、麻酔の効きが悪いように感じたら、すぐに歯科医師に伝えるようにしましょう。麻酔を追加するなどの処置を行います。
抜歯した後は痛みが出るの?
抜歯をした後、麻酔が切れた後に、痛みが出ることがあります。
特に親知らずの抜歯で、顎の骨を削るような症例では、痛みや腫れが起きやすくなります。
痛みのピークは術後2日〜3日です。1週間程度で徐々に治まってきますので、鎮痛剤を利用しながら安静にして過ごすようにしましょう。
歯を抜いた後に注意することは?
歯を抜いた後、痛みや腫れを出来るだけ抑え、傷の治りを良くするためには、いくつかの注意点があります。
抜歯後の注意点をあげていきます。
激しい運動や入浴、飲酒を控える
血の巡りが良くなるようなことは控えるのが良いです。激しい運動や入浴、飲酒は、血行を良くし、痛みを増幅させてしまう可能性があります。
入浴はシャワー程度で済ませるようにしましょう。
なるべく安静にして過ごすのが痛みや腫れを抑えるポイントです。
なるべくうがいをしない
抜歯をした後は、血餅(けっぺい)という血の塊ができ、カサブタの役割をはたします。
頻繁にうがいをすると、血餅が剥がれ落ちてしまい治りが悪くなったり、痛みが出ることがあります。なるべくうがいをしないようにして過ごしましょう。
処方された薬は用法通りに服用する
抜歯後は、鎮痛剤と抗生物質が処方されることが多いです。
鎮痛剤は痛みがある時に服用し、抗生物質は必ず用法通りに服用するようにしましょう。
まとめ
今回は、抜歯にかかる費用や、親知らずのケースを中心に、抜歯時に知っておきたいポイントを解説していきました。
安心して抜歯をするための参考にしてください。抜歯をする場合には、事前にレントゲン検査等を行い、抜歯の必要があるかの診断を行なっていきます。
初診の方への抜歯に関するお悩みなども伺いますので、抜歯に関わる不安がある場合には、ぜひご相談ください。
抜歯をした後は、親知らずでなければ、失った歯を補う治療をしなくてはなりません。当院では、抜歯後の治療も行います。インプラントや入れ歯、ブリッジの選択肢がありますので、歯科医師とよく相談して治療方法を決めていきましょう。